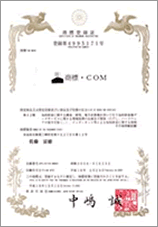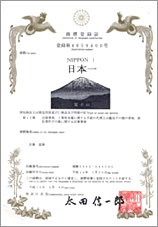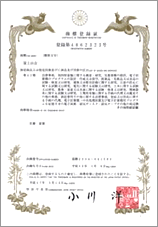-先願特許権者は後願特許発明を自由に実施できるか?
先願特許発明と後願特許発明との利用抵触関係について
―先願特許権者は後願特許発明を自由に実施できるか?―
先願特許発明と後願特許発明との利用抵触関係について
斎藤質問
佐藤論説では、先願特許発明を後願特許発明が利用する場合、先願特許権者は後願特許発明を自由に実施できるか?ということについて、主として論じておられるが、逆に、先願特許発明が後願特許発明を利用する場合、先願特許権者は後願特許発明を自由に実施できるか?ということにについて、質問致します。
もし、判例がありましたら、判例に基づいて御教示して戴けたら有り難いと思います。
さらに、判例と各説との関係についても触れて戴いたらと思います。
回答(斎藤質問)
1.最初の質問(逆に、先願特許発明が後願特許発明を利用する場合)について
斎藤先生の質問に限らず、特に断らない限り、以下両権説に基いて説明することに致します。先願特許発明を後願特許発明が利用する場合については、特許法第72条が適用され、後願特許権者は、後願特許発明を自由に実施することができないことには、疑いの余地はないであろうと考えられます。1)
逆に、先願特許発明が後願特許発明を利用する場合については、抵触の場合と同様、特許法には規定されていないのです。先願特許発明の実施は後願特許を実施することになるので、文言上侵害を構成することとなるとも考えられます。
従って、このような場合どのように考えたら良いかは、特許法の法目的等から合目的に解釈する必要があります。
先願特許発明A+B+Cであれば、後願特許発明A+Bは、特許法第29条の2(拡大された先願の地位)の特許要件違反で拒絶されるのが一般的と考えられます。2)
なお、特許法の文言上は、先願特許権者は先願特許発明A+B+Cを実施すれば、一般には、後願特許発明A+Bを実施することになります。逆に、後願特許権者が、先願特許発明A+B+Cを実施すれば、当然のことかがら、先願特許発明A+B+Cを実施することになります。
特許法での相抵触特許の権利調整規定はないのであり、如何に取扱いをしたら良いのでしょうか?このような場合、単に特許法の中の特許の抵触として把握するのではなく、工業所有権(特に、特許法、実用新案法、意匠法)の中で、保護対象としての創作物は権利化されれば、抵触すると言うのは、広く一般に認められているところであります。米国の場合は、意匠も発明として把握しているのであり、意匠も発明も創作物という点では、格別の差はないと考えられます。
してみると、特許発明と登録意匠等と抵触する場合の取扱い(特許法第72条)と同様に取扱うべきでないでしょうか?このように考えても、何ら不合理は生じないと考えられます。
特許法法72条を類推解釈以外に適当な調整手段というものは私には思い浮かばないのです。
2.2番目の質問(判例に基づいての教示)について3)
ここに、判例(平成7年(ワ)第3436号 損害賠償請求事件があるので、それを簡単に紹介することにしましょう。
本件は、後願の実用新案権者である原告Kが、先願のS社の特許権者に対して、先願特許発明が後願登録実用新案を利用する関係に有る場合、被告S社の先願特許発明の実施は原告Kの後願登録実用新案権を侵害することとなるとして訴えていた事件であります。
しかし、判決では、「ところで、被告製品は、前記1のとおり本件考案の先願にかかる被告特許発明の実施品4)でもあるところ、先願にかかる他人の特許権等との関係を定めた実用新案法17条、26条(特許法第81条)の趣旨に照らし、先願にかかる被告特許発明の特許権者で有った被告S社は、後願たる本件実用新案権の禁止権によって制約されることなく、被告特許発明を実施することができたものと解するのが相当である。したがって、被告製品の製造販売は、結局、本件実用新案権を侵害するものではないといわなければならない(なお、被告特許権の存続期間満了後については、被告は、実用新案法26条、特許法81条の類推適用により、本件実用新案権につき通常実施権を有したものと解するのが相当である。)。」と判示しています。私も判決の結論自体には賛成でありますが、判決も私の主張する両権説を意識してはいないが、両権説に従って判断したとしても差し替えない部分が有る点留意すべきであろうと考えます。5)
また、ちょうど公知技術除外説と同様に、原告の後願特許の請求範囲の解釈に当って、被告の先願の技術範囲を除外して限定的に解釈し、 また、増井和夫・田村善之共著 「判例工業所有権法」1996年3月10日 初版第1刷 有斐閣発行211~212頁にも、「その結果、先願の特許のまま実施する被告装置について、後願の特許権を侵害するものではないと判示した判決がある。(大阪地判平成4.8.27判例工業所有権法〔2期判〕2293の31頁「魚の卵巣取出し装置」)。理屈はともかく、狙いとする帰結は正当であろう。」6)とあります。
3.3番目の質問(判例と各説との関係)について
両権説では、利用抵触関係の権利調整は、先願特許の専用権とは、後願特許の排他権との強弱(相手の矛と自己の盾)ということに帰結致します。両権説の利点は、イ号が自己の専用権かどうか、イ号が他人の排他権か否かの二つを判断すればよいので点の判断をすれば足りる得るといういうことであります。
私見ではありますが、両権説に従えば、後願の権利範囲の中に公知事実除外説のような複雑な判断をするまでもなく、先願の排他権と後願の専用権の強弱を判断することで足りると考えられるのです。
これに対して、専用権説では、イ号が自己の専用権かどうかの判断の他、自己の専用権と他人の専用権が利用抵触関係にあるかどうかをも判断する必要があるということであります。
両権説では点の判断で良いが、専用権説の判断は面の判断をする必要があるので、過去の経緯を見ても判断が煩雑となる場合も有るのではないかと考えられます。7)
また、同一の発明について過誤特許された場合には後願特許は無効理由を有するが、後願特許権には積極利用権が有るとして、後願特許発明の実施は侵害を構成しないとした判決8)も有る。(ただし、これに対しては強い批判がある。9))
また、一方、上記判決に対立する判決、すなわち、特許の有効無効に拘らず、後願特許発明の実施は先願特許権を侵害している事実に変わらないとした判決も有る。10)
両権説も専用権説も専用権を前提するのであるが、専用権は国家から特許権を附与されて特許発明の実施を一定の例外を除いて保証される11)という権利者保護の点からは非常にメリットがあると考えられます。ベンチャー企業育成の面からも法目的に合致すると考えられるからであります。
排他権の場合は、排他権は国家が保証するが専用権については保証の限りではなく、私的自治に任せるというのであり、権利者保護の点からはデメリットがあると考えられます。
さらに、排他権説では、イ号が自己の専用権の内容かどうかはさて置き、イ号が他人の排他権に入っているかどうかの判断のみで足りるので取扱いは非常に簡単となるというメリットがあります。
ただし、この説には、現在の我国の特許法の規定(特許法第68条)は、排他権説に従って規定していないという難点も有ります。
4.おわりに
最後に、一つの結論として、先願特許権者が自己の先願特許発明A+B+Cそのまま実施している場合、後願特許発明(A+B、あるいはA+B+C+D)を実施することになったとしても、自由に実施することができるとして問題なければ、その方が単純化され望ましいと思います。先願特許権者が自己の先願特許発明A+B+Cそのままの形で実施している場合(イ号発明もA+B+Cの場合)、イ号発明が後願特許の排他権の範囲内に入る否かを何ら判断するまでもなく自由に実施できるというものです。
何故ならば、先願特許の専用権は後願特許の排他権よりも強力であって制限されることはないと思われるからです。12)
以上
注
1) 東京高判昭和34.2.24判時181号6頁「バトミントン羽子」を参照のこと。
2) しかし、特許法第29条の2の規定は、主体的要件として、発明者同一の場合、又は出願人同一の場合には、適用されません。査定審決後に権利主体が変更された場合には、斎藤先生の御指摘のような場合が現実に発生することとなると思います。
また、先願特許発明A+B+Cに対して、構成要件Cを省略することは不可能と考えられていたような場合において、省略しない場合の発明と比較して同程度の効果を発揮するような後願特許発明A+Bを発明した場合も同様であります。
3) 誌上研究発表会開催に当っての中で、「委員会での議論の一部をかいつまんで紹介させていただきます。……途中省略……」として、「論文毎に思わせぶりなことを書かせていただきましたが、……。」と書いておられる中で、私の論文については、「研究として興味深いが、判例に支えられた議論がなく、法律論文と言えるのだろうかという議論があった。」と有りました。
しかし、このような指摘は、当を得ていないと私には考えられます。
何故ならば、元々、法律論文とは、どのようなものを言うのかという根本問題に帰一することになろうが、「法律論文とは、法律に関する論文を法律論文という」のであろうと考えられます。法律論文に、判例が必須であるとは必ずしも考えられないのであります。判例のみに捕らわれると、逆に単なる過去の判例解説のみに終始して、論文に必須のオリジナルティが無くなるということにもなるのではないでしょうか?
4) 被告特許発明の実施品は明細書に示された実施例そのものです。
5) 例えば、「先願にかかる他人の特許権等との関係を定めた実用新案法17条、26条(特許法81条)の趣旨に照らし、先願にかかる被告特許発明の特許権者で有った被告は、後願たる本件実用新案権の禁止権によって制約されることなく、被告特許発明を実施することができたものと解するのが相当であります。」と判示されています。
6) 増井和夫・田村善之共著 「判例工業所有権法」1996年3月10日 初版第1刷 有斐閣発行211~212頁を参照。
7) 利用関係の判断は、そっくり説、実施上の利用説、不可避説等各説が有り、過去から、非常に複雑な判断を強いられることとなっています。しかし、利用抵触については、自己の特許発明(イ号発明)そのものを実施すれば、他人の特許権等(実用新案権、意匠権、商標権)の排他権の範囲内に入るか否かで判断できれば、それ以上に利用抵触関係に該当するか否かの判断をする必要もないと考えられます。利用関係であるか抵触関係かも区別必要ないとも考えられます。
8) 京都地判昭和46.5.7無体集3巻1号197頁[組立ブロック玩具]、大阪地判昭和33.9.11判時162号23頁[クロルプリマジン]、山口地判昭和39.4.30判時391号32頁[ポリプロピレン重合触媒]
9) 例えば、竹田和彦は、「しかし、この立場を採用すると、後願が先願と同一になった方が先願を改良して利用発明となった場合よりも有利となり、座りの悪さを否めない。理論的に考えてみても、審査官は後願が先願の発明の技術的範囲に属すると考えたとしても、利用発明である場合には、結局、後願の発明につき特許権の成立を認めるものであるから、後願の特許権が附与されたということは何ら後願が先願の技術範囲に属しないということを意味しないはずである。さらにいえば、特許権を有していても、利用関係に立つ先願が存する場合には先願の特許権を侵害することに異論はなく、そもそも積極的利用権があるということ自体誤りである。」としている(竹田和彦、特許の知識(1988年・ダイヤモンド社)355~359頁)。
10) 浦和地判昭和48.10.5判例特許実用新案法1050の18頁[ビタミンB2脂肪酸エステルの製法]、東京地判昭和47.9.27判タ288号277頁[メトカルバナール]、水戸地判昭和48.2.22判タ295号366頁[納豆包装]
11) 先願特許権者が自己の先願特許発明A+B+Cそのままの形で実施している場合(イ号発明もA+B+Cの場合)、イ号発明の実施が保証されているとも考えられます。イ号発明が後願特許の排他権の範囲内に入る否かを何ら判断するまでもなく実施が保証されていると考えることもできます。(上記は両権説)
12) 増井和夫・田村善之共著 「判例工業所有権法」1996年3月10日 初版第1刷 有斐閣発行211~212頁にも、「しかし、本判決のように単に被告製品と先願の実用新案権の技術範囲に属するとの一事をもってただちに後願後願の意匠権にかかる意匠をも実施することができることは、他人の創作した意匠を模倣して実施することをも許容することになりかねず、意匠制度の趣旨に反する事態を招く(実際に、被告が被告製品を発売したのは昭和43年10月22日であり、本件意匠が意匠公報に掲載された40年11月26日以降のことである。)」先願の抗弁を認めるとしても、先願の実用新案権の明細書や図面の中に開示されている製品の形態の限度に止めるべきである。(竹田和彦「評釈」判例特許侵害法〔馬瀬古希1983年・発明協会〕600頁)」とあります。
市川質問
既に幾つかの論文において、パラメーター発明に関し、特許権の錯綜についての懸念が示されているようです。それからも窺えるように、特許権同士の抵触は、今後、実務上において問題視される場面が増えてくるような気がします。
ところで、特許法が特許権同士の抵触を予定していないのは、直接的には同法39条が重複特許を排除し、また、間接的には同法81条が抵触する意匠権との調整のみ規定しているためと一般には理解されているといると思います。そこで、最初の質問ですが、後願特許が先願特許権と抵触する場合、特に、後願特許発明の実施の態様と先願特許発明の実施の態様が重複している場合、原則通り後願特許権を法39条で排除することはできないものでしょうか?この点、審査基準が39条に関し「実施の態様が一部重複し得るとしても技術的思想が異なれば同一の発明としない」と表明してあることにもご考慮いただき、ご回答いただければ幸いです。
次に、佐藤先生は、抵触し合う先願特許権と後願特許権とが併存している場合の取扱いにお考えを示されているのですが、先願特許権が存続期間満了により消滅した場合の取扱いには言及されていないようです。この点、どのようにお考えでしょうか。後願特許権の存在を理由として、先願特許権者であった者の実施が制限されることになるのでしょうか。それとも、法81条を援用して調整を図るのでしょうか。或いは、他の手段による調整を図ることになるのでしょうか
回答(市川質問)
質問の冒頭において、市川先生は「パラメーター特許に関しては、特許権の錯綜についての懸念が示されており、特許権同士の抵触は、今後、実務上において問題視される場面が増えてくるような気がします。」とご指摘されておられますが、プロパテントの追い風1)の中、私も全く同感であります。
特許権同士の抵触には、審査の困難性に基因する過誤特許の場合と、過誤特許でなくとも選択発明、用途限定発明の場合(5月号論文を参照して下さい。)の両方が考えられますが、兎に角利用抵触問題として問題視される場面が今後とも増加していくことは間違いのないところであろうと確信しております。
理論上では、審査の困難性の問題は残りますが、パラメーター特許に関してキチンと審査を行なうことができれば、特許権同士の抵触の問題は一応は回避できることになります。パラメーター特許の抵触の問題の本質は、異なった表現をしても同一発明はやはり同一発明であるということに帰結するのではないでしょうか?パラメーター特許に関する抵触特許権の中には無効理由を有する瑕疵有る特許も多く含まれると思われますし、無効審決が確定するまでの特許抵触状態をどのように扱うのかという問題もあると考えられます。
一般に理解されている「特許法第39条が有るから重複特許を排除するので抵触関係を生ずることは有り得ない」とする考え方(質問で言う直接的理由)或いは「「特許法第39条が有るから重複特許を排除して抵触関係を生ずることは有り得ないから、特許権同士の特許権同士の権利調整は規定していない(特許法第72条)という考え方(質問で言う間接的理由)が一般的には考えられているようです。私はこのような考え方は間違っていると考えます。
直接的理由については、既に私の5月号論説において、選択発明、用途限定物発明等の具体例を挙げて、特許法第39条等の特許要件をクリアして特許となっても、先願特許発明A+Bと後願特許発明A+B+Cにおいて、抵触関係を生じる場合については既に十分論じた積もりであります。
1.最初の質問(実施の態様の重複と特許法第39条との関係)について
御質問の場合の実施の態様A0+B0+C0)2)が重複している場合、先願特許権者と後願特許権者が共に実施の態様A0+B0+C0を実施する場合、抵触問題を生じさせる場合が有り得るという危惧は容易に推測されます。しかし、実施の態様A0+B0+C0が重複している場合、特許法第39条で排除されるはずではないでしょうか?特許法第39条で排除されるのであれば、特許法上では抵触は生じないとする通説に反するのではないでしょうか?それに対してどのように考えたら良いのでしょうかというのが市川先生の御質問の趣旨であろうと考えます。私の5月号論文において、先願特許発明A+Bに対して、後願特許発明A+B+Cとする場合、ここにおいて、先願特許発明A+Bの実施態様は共にA0+B0+C0で重複している場合について、考察を加えることに致します。先願特許発明A+Bの実施の態様は、【発明の詳細な説明】に実際に【実施の態様】の個所において、記載された実施の態様A0+B0+C0のうちA0+B0であると解すべきであろうと考えます(C0が外的付加の場合)。C0は先願特許発明A+Bの実施の態様には必須ではなく、不必要な限定をしたものと考えるべきです。後願特許発明A+B+Cの実施の態様は、当然A0+B0+C0です。ただし、C0が内的付加の場合は、構成要件A、Bの何れかをさらにC0により具体的に限定したものと考えられ、先願特許発明A+Bと後願特許発明A+B+Cの間で、実施の態様A0+B0+C0は、共通にすることになります。
内的付加であっても外的付加であっても解釈上の差は有るが、後願特許発明A+B+Cの構成要件Cに特徴があれば、先願特許発明A+Bと後願特許発明A+B+Cとは技術思想が相違することになり、両発明は明確に区別し得ることになります。
審査基準において、特許法第39条に関し「実施の態様が一部重複し得るとしても」とあるのは、クレーム記載の両発明が明確に区別できれば、詳細な説明の実施態様が例え重複していても、特許法第39条は適用されないということを言っていると思われます。
先願特許権者は、自らの特許明細書の中で、実施の態様として、A0+B0+C0を記載しているので、当然実施の態様A0+B0+C0を実施できると主張してきます。
しかし、外的付加の場合、先願特許発明A+Bの実施の態様はA0+B0であり、C0は【実施の態様】の個所に記載されてはいますが、特許クレームに記載されていないのです。すなわち、実施の態様A0+B0+C0がクレームに記載されていない以上、実施の態様A0+B0+C0は権利取得を放棄したと考えるのが自然であろうと思います。
「実施の態様が一部重複し得るとしても」とあるのは、やや厳格性を欠いた表現であると考えられます。例えば、「先願特許発明A+Bの【発明の詳細な説明】中の【実施の態様】に、発明者がクレームアップした発明の実施の態様であると考えたものを実施の態様としてA0+B0+C0を記載されていた場合、実施の態様が一部重複し得るような場合であっても」と解するのが妥当だからであります。
従って、先願特許発明A+Bを取得した先願特許権者が自らの実施の態様と信ずるA0+B0+C0を実施していた場合、後願特許発明A+B+Cの実施することになり、逆に後願特許権者も後願特許発明A+B+Cの実施の態様A0+B0+C0を実施すれば、先願特許発明A+Bの実施となり、いわゆる抵触関係を生ずることがあり得ると考えられます(外的付加の場合)。
1.2番目の質問(先願特許権が存続期間満了により消滅して場合の取扱い)について
相抵触する特許権のうち、先願特許権が存続期間満了により消滅した場合はどのように取扱えば良いかということが問題となります。殆どの場合、先願特許権の方が、後願特許権よりも先に存続期間満了により消滅するであろうと考えられます。先願特許権が先に存続期間満了により消滅した場合でかつ後願特許権が未だ存続している場合に、先願特許権者は先願特許発明であったA+Bを自由に実施できるのか否かということであろうと推察致します。特許法での相抵触する特許同士の権利調整規定は存在しないのであり、如何なる取扱いをしたら良いのでしょうか?質問において御指摘されておられるように、特許法の中の特許の抵触として把握するのではなく、工業所有権(特に、特許法、実用新案法、意匠法)の中で、保護対象としての創作物は権利化されれば、抵触すると言うのは、広く一般に認められるところであります。米国の場合は、意匠も発明として把握されているのであり、意匠も発明も創作物という点では差はないと考えられます。してみれば、特許法では特許権同士の抵触は予定していないとして有り得ないというのではなく、選択発明とか用途限定物の発明の場合は、抵触関係が極普通に生じ得るのであります。特許発明と登録意匠等と抵触する場合の取扱いと同様に取扱うべきであろうと考えられます。このように考えても、何ら不合理は生じないと考えられます。
すなわち、先願特許権が存続期間満了により消滅した場合の取扱いは、特許法第81条を類推解釈して、先願特許権者であった者の実施が制限されないと解釈するのが妥当ではないでしょうか?特許法第81条を類推解釈以外の他の調整手段というものは私には思い浮かばないように思われるのです。
なお、先願特許権が存続期間満了により消滅した場合であっても、後に無効理由が判明した場合には、特許権消滅後であっても無効により遡及的に特許権が消滅する場合が有り、かかる場合は、特許法法第81条の先願権利者に該当しなくなることになるでしょう。この様な場合は、当然、先願特許権者で有った者は、後願特許発明A+B+Cを自由には実施することができなくなり、実施すれば侵害となり得るのではないでしょうか。
付言するならば、無効理由が有るか否かの判断は、一般的には微妙な進歩性の判断を必要とするので、瑕疵有る特許であっても有効に存続する限り、特許法第81条の類推解釈が適用されると考えた方が良いのではないでしょうか?後願特許権の無効消滅を待たないで、特許法第81条の類推解釈を適用して、先願特許権が後願特許発明A+B+Cとした方が、無用な争いを法廷まで持ち込まなくても良い場合も有ると考えられます。権利調整を積極的に図っていく方が、法解釈上優れているのではないでしょうか?
注
1)プロパテントの追い風下、抵触問題が重要になっていくと考えるのは、損害賠償額の高騰にも依拠していると考えます。30億円損害賠償事件(H2ブロッカー事件)の判決において、逸失利益の算定方法は、今回の改正特許法を先取りしたものであり、我が国の賠償事件としては過去最高額となりました。この判決が契機となって、我が国の本格的プロパテント時代の幕開けを反映したものということができるからであります。
2)実施の態様A0+B0+C0において、A0、B0、C0は夫々、構成要件A、B、Cをさらに具体的に限定したものであります。
糟谷質問
省略
回答(糟谷質問)
糟谷先生には、私の拙稿に対して貴重なご意見を賜り、深く感謝するとともに、厚くお礼を申し上げます。
1.専用権と排他権と両権説の根拠について
先ず、各権説の根拠がハッキリしていないとのご指摘について回答致します。糟谷先生の持論としての期限付き「排他権」については、2.特許法の存立根拠のところで触れたいと思います。
物権と特許権(他の工業所有権をも含む。)との比較を纏めて見ると以下のようになります。
表1 物権と特許権との比較
物権
特許権
権利対象
有体物
無体物
性質
1物1権
1発明1特許
(重複特許排除)
権利行使
利用抵触関係が
生じない。
利用抵触関係が
生じ得る。
効力
排他的支配権
排他的独占権
無体物の得失により、権利内容が不明確、事実上の不可能等が生じます。
物権の存立根拠はさて置き、特許制度については、公開代償説、発明奨励説が有力であります。ただし、今日一個人ではなく、企業が権利を取得して、経営資源の一つとして、特許権を活用するようにインセンティブを発揮し得るように考えることが、特許制度の根拠を説明する上で重要であろうと考えます。公開代償説は、特許制度導入して間もない初期の段階では、国家的観点からは有用であったでしょうが、これだけでは、今では説得力有る根拠たり得ないように思われます。自由主義経済下では、厳しい技術開発競争に晒されるのでありますが、最先に先行投資して新規技術を開発した者に、特許制度に基く“超過利潤”を与えない場合には、開発費用を掛けないで模倣した者の方が、その分、価格競争に勝利して利潤を得るというのは不合理であると考えられます。技術開発の種を播かない者が収穫を得るという不合理な構造を排除することが重要であります。特許制度は、コストを掛けた開発者に先行投資の回収をするための“超過利潤”を確保して、我国の産業の発達を図っていくためのものであると思います。簡単かつ手短に言えば、21世紀の我国の産業の国際的競争力を発揮して行くためには、我国の特許制度は如何にあるべきかを考えて、それに相応しい特許制度(運用を含む。)を考えることが重要であろうと思います。
物権の1物1権主義に対して、特許制度では、1発明1特許すなわち重複特許排除の規定(特許法第39条、実質的には特許法第29条の2)によって、重複特許は有り得ないないことになっています。
しかし、同じ発明については、同一の権利は理論上ないことになっているが、権利行使の際には、別途考慮すべきであろうと考えられます。
専用権の行使をする場合に、他人の特許権と利用抵触関係を生ずる場合が有り得ますので、利用抵触関係に有る特許権同士を権利調整することが重要であります。なお、このような趣旨に関しては、既に私の5月号論文で具体例も挙げて述べたところであります。
各説の比較については、斎藤先生への回答をご参照下さい。
2.特許法の存立根拠
質問では、特許権の根拠が、資本論の特別余剰価値を根拠に排他権であるべきであるとしておられますが、産業政策的観点から、特許権が排他的効力を有することには、正面切って反対する者は先ずいないと考えられます。
企業が先行投資をした開発費回収ができるように、技術開発を活発化して技術の累積的進歩、新規発明の誕生により“超過利潤”を目論むことができるシステムにすることが、特許制度の存在根拠となるのではないでしょうか?そのためには、自由主義経済下では、排他的独占権とすることに大きな間違いはないと考えられます。自由主義経済下では、発明者証の方がベターであると考える者は皆無に近いと考えられましょう。私が5月号論文で特に強調したかったのは、我国特許制度は、1物1権主義で重複特許を排除するが、権利行使する場合には利用抵触関係を生ずることが極普通に有り得るので、その権利調整を円滑にするためにはどうしたら良いかを主テーマとして取上げたものであります。権利調整方法の説として、3つの説を取上げて説明致しました。責任をもって利用抵触について的確に見極めるということは、見た目以上にプレッシャーの中では難しいと感じましたものですから、5月号論文にて取上げたのです。
1mの高さの平均台を渡ることは誰でもできるが、100mの高さの平均台を渡ることはプロでなければできないものです。
なお、特許権の存続期間については、物権が、実質的には、対象物が消滅するまでであるのに対して、技術が陳腐化して保護価値がなくなるので、特許権の存続期間を一定期間として特許制度の法目的をより有効に達成しようとしていることも議論の余地はないであろうと考えられます。存続期間に対しては、私の論文の論点とは直接は関係ないので、これ以上は触れないことに致します。
「なお、時代遅れとなった技術は誰にも使われません。」「使われない技術は誰にも使われません。」とありますが、少し緻密さを欠くと思われます。出願から期間が経過して行っても、なお価値を有する基本発明があるものです。先願特許発明A+Bが陳腐化して、例え、経済的には、改良特許発明A+B+Cの方がより価値が高くなったとしても、先願発明A+Bの発明にも、なお価値が有り得ると考えられます。陳腐化するから保護を与えないと考えても良い場合が有りますが、余り長い保護すなわち手厚い保護を与えると特許権者は特許権の上に胡座をかいて発明努力を怠り日本の国際的技術競争力を高めるのに貢献しないのではないでしょうか?その弊害防止を図るために、特許権の存続期間を定めていると考えた方が素直ではないでしょうか?
3.分析ツール、論理ツール
有体物の代表である不動産についても、不動産の価値は必ず上昇すると言う土地神話が崩れて、逆に21世紀には無体物の特許権の価値が向上していくようにも考えられます。
物権と特許権との1物1権主義と1発明1特許の原則とは物権の方がより厳格に成立するという差があろうがそれ程の差はないであろうと考えられます。
ただし、権利行使の場合に、利用抵触関係が生じ得るということが大きな差ではないでしょうか?質問の中で指摘されているように「しかしながら特許権はそうでは有りません。技術的な「思想」たる発明を権利客体とするものであります。基本発明も有れば、改良発明もあり、時系列的にも錯綜して、現象生起するものであります。ある権利の内にいつの間にか他の権利が発生することは日常茶飯事と思います。」と書かれておられますが、後願特許発明が先願特許発明を利用する場合については、特許法第72条の規定も設けておられることから考えても、全くおっしゃられる通りであると思います。しかし、私はさらに、特許同士にも抵触が起こり得ることを具体例を掲げて、権利調整をどのようにしたらよいかを論じた積もりであります。
論理ツール、分析ツールについては、少なくとも、論理ツール、分析ツールに相当すると考えられるものは、既にかなりの内容を5月号論文で論じた積もりであります。
4.論理学と集合論と文法
請求項に記載の発明が構成要件A、B、Cで記載されることには異論は全くありません。各構成要件A、B、Cが内包として表現されるという考え方にも特に異論はありません。外延は、内包によって定義された個々の物、個物の集合であると言われておられ、また文法が論理文と自然語との間を媒介する等については、私の5月号論文の論点ではないので、浅学の私が深く触れることは憚られるので、割愛することに致します。
質問の中に有る「ここで先ず、記号について若干説明致します。貴論では「+」が使われていますが、その意味がはっきりしない。普通「+」は、論理語では「or」あるいは「または」の意味で用いられているのではないか。」と有ることについて回答致します。請求項に記載の発明を“構成要件A、B、Cから成る何々”という具合に表現するのが、通常になっているのではないでしょうか?
してみると、「+」という記号は使っていますが、実質的には、集合論の意味では、「×」と同義であると考えられる。すなわち、“後願特許発明A+B+C=後願特許発明A×B×C”と表現できることになります。
従って、私の表記法の「+」を糟谷先生の表記法の「×」に置き換えれば、糟谷先生の「ここで、厳格に定義すると以下のようになると思います。」とあり、それ以降に記載されてあることには、私も糟谷先生の主張の通りであると考えます。ハッセ図とかオイラー図とかの説明も非常に理解し易いと思います。
また、穴空き特許については、先願特許発明A+Bから後願特許発明A+B+Cを除いた部分(補集合)が穴空き特許ではないか?と質問されていますが、私の言う穴空き特許は、先願特許発明A+Bであっても、例えば、効力を奏しない部分を有する先願特許発明A+Bが穴空き特許であると言う意味であります。穴が空いている1)というのは、スキが有るという意味であり、その部分は後願であっても、特許取得され得る可能性が有るということであり、先願者としては気を付けなければならないと言うことを強調したかったのです。
なお、「そこで先後願については、Aが先願の場合は、AB以下は特許になると思いますが、例えばABが先願でAが後願の場合は拒絶になると思います。」とありますが、大雑把な議論としてはその通りであると思います。ただし、もう少し緻密な議論としては、私の5月論文および斎藤先生への回答を参照して戴ければと思います。
以上
注
1)特許請求の範囲の記載からすれば、形式的にはその範囲内に包含されるものであっても、その発明の作用効果を奏しないものは、技術的範囲に属しない。発明は、その作用効果を奏してこそ発明たり得るのであるから、その作用効果を奏しないものにまで技術範囲を及ぼすべきでないからである。
また、技術的範囲が広すぎるため作用効果を奏しない部分を含む場合も、同様の理由により、その作用効果を奏しない部分に該当する技術は技術範囲に属しない。(吉藤幸朔著、熊谷健一補訂「特許法概説(第12版)」有斐閣発行, p.509)
弁理士・行政書士 佐藤富徳
| 特許事務所 富士山会 | |
代表者 弁理士 佐藤富徳 |
|
| 電話 | 0120-149-331 |
| ファックス | 0120-149-332 |
| メールアドレス | fuji3kai@sweet.ocn.ne.jp |
| HPアドレス | 知的財産権の年金専用サイト |